犬の炎症性腸疾患と腸内フローラの機能的視点 |善玉・悪玉の時代から機能性評価へ
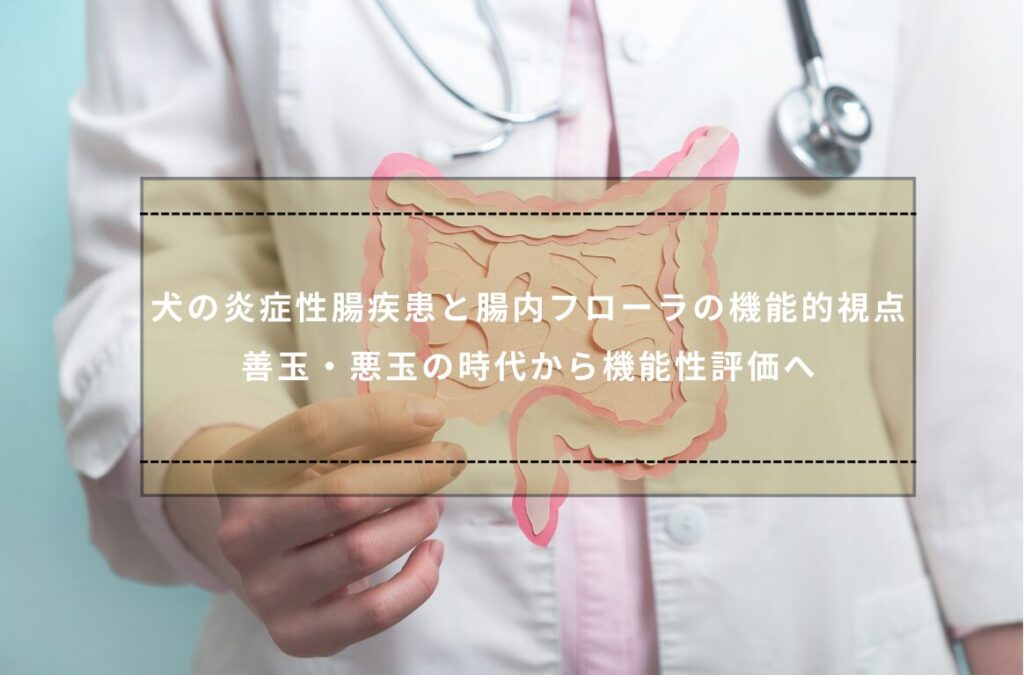
はじめに
これまで腸内フローラの議論では、「善玉菌」「悪玉菌」といった二項対立で語られることが多くありました。しかし、近年のマイクロバイオーム研究では、細菌の代謝産物や免疫系への作用など、“機能”に基づく評価も注目されています。
特に、慢性腸症(CE)や炎症性腸疾患(IBD)においては、腸内細菌のバランスが崩れた「ディスバイオーシス」が発症・維持に関わることが明らかになっており、単に「どの菌がいるか」よりも、「その菌が何をしているか」に注目すべきだと考えられています。
この記事では、IBDにおける「機能的に有益な腸内細菌」について、主にその代謝産物や免疫調整作用に基づいて紹介します。
※ほぼ私の知識のアップデートになりますので、見づらさはご了承ください。
炎症性腸疾患において「有益」とされる機能とは?
IBDに対する有益な腸内細菌とは、単に存在しているだけでなく、以下のような代謝や機能を持つ菌群を指します。
1. 短鎖脂肪酸(SCFA)の産生
- 酪酸、酢酸、プロピオン酸など
- 腸上皮のエネルギー源、粘膜バリアの修復、炎症抑制などに関与
2. 粘膜バリアの強化
- タイトジャンクションの維持、粘液分泌促進
- 病原菌の侵入防止
3. 抗炎症性免疫の誘導
- 制御性T細胞(Treg)の誘導、IL-10産生促進、Th17抑制など
- NF-κB経路の抑制によるサイトカイン産生の制御
有益な代謝機能をもつ代表的な腸内細菌
| 菌名 | 主な機能 | 補足情報 |
|---|---|---|
| Faecalibacterium prausnitzii | 酪酸産生、IL-10誘導、抗炎症因子の分泌 | ヒトのIBDでは顕著に減少し、「抗炎症性細菌」の代表格とされる |
| Eubacterium rectale | 酪酸産生 | 腸上皮の栄養供給源として、粘膜修復をサポート |
| Roseburia spp. | 酪酸産生、Treg誘導 | 粘液分泌との関連も報告される |
| Clostridium cluster IV, XIVa(例:Ruminococcus, Blautia) | SCFA産生、Treg誘導 | 炎症抑制に寄与する複数の機能性菌が含まれる |
| Bifidobacterium spp. | 酢酸・乳酸産生、pH低下、病原菌抑制 | 一部株はTreg誘導やバリア強化に関与 |
| Lactobacillus spp. | 乳酸産生、抗菌ペプチド分泌、粘膜バリア支持 | 株により抗炎症性が異なる |
| Akkermansia muciniphila | 粘液分解、バリア機能促進、免疫調整 | ヒトでの抗炎症性が注目されており、動物モデルでの有効性も示唆されている |
Fusobacteriumのような「減少=善玉?」の再考
一部の研究では、犬のIBDでFusobacteriumが減少するという報告があります。しかし、それをもって「有益菌である」と解釈することには注意が必要です。
- Fusobacterium属には病原性を持つ種も多く(例:F. nucleatum)、ヒトでは炎症性疾患や腫瘍との関連が指摘されている。
- 一部は硫化水素やアンモニアなどの有害代謝産物を産生し、腸粘膜に悪影響を及ぼす可能性がある。
- 減少は炎症環境の結果に過ぎず、その菌自体が炎症を抑えるわけではないとする見解もある。
つまり、「減っている=善玉だった」は必ずしも正しくなく、代謝機能や免疫との相互作用の文脈で判断する必要があるのです。
今後の展望:機能性マイクロバイオータへのシフト
今後の腸内フローラ研究と臨床応用においては、以下の視点がより重要になると考えられます:
- 属や種レベルではなく、株レベルやメタボロームに基づく評価
- 細菌の代謝経路(例:酪酸合成経路)や免疫調整機能に着目
- 単一菌ではなく、菌群としての機能ユニット(functional guild)の理解
- 犬種、年齢、食餌、環境要因との複雑な相互作用の考慮
おわりに
「この菌は善玉?悪玉?」という単純な分類では、複雑な腸内フローラの働きを捉えるには不十分です。特に炎症性腸疾患のような慢性疾患においては、“何をしている菌か”を見極める機能的アプローチが重要と考えられます。
今後、プロバイオティクスや食事療法の選択にも、こうした「機能性マイクロバイオータ」の概念が反映されていくことが期待されます。
関連記事
LILINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで消化器症状でお悩みの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。
参考文献一覧
1. Minamoto Y, et al. (2015)
Title: Alteration of the fecal microbiota and serum metabolite profiles in dogs with idiopathic inflammatory bowel disease
Journal: Gut Microbes
- 目的: 犬のIBDにおける糞便中の腸内細菌叢と血清代謝物の変化を調査。
- 主な結果:
- IBD犬ではFirmicutesの減少とProteobacteriaの増加が顕著。
- 特にFaecalibacteriumなどのSCFA産生菌が減少。
- 代謝物プロファイルも異常(アミノ酸代謝の変化など)。
- ポイント: 腸内細菌と代謝産物の両面からIBDの病態に迫った先駆的研究。
2. Suchodolski JS, et al. (2012)
Title: The fecal microbiome in dogs with acute diarrhea and idiopathic inflammatory bowel disease
Journal: PLoS ONE
- 目的: 犬の急性下痢とIBDにおける糞便マイクロバイオームの比較。
- 主な結果:
- 急性下痢よりもIBDのほうが**腸内フローラの撹乱(ディスバイオーシス)**が深刻。
- Fusobacterium, Ruminococcaceae, Bacteroidetesなどの減少。
- ポイント: ディスバイオーシスの“慢性化”がIBDに特徴的であることを示唆。
3. Pilla R & Suchodolski JS. (2021)
Title: The role of the canine gut microbiome and metabolome in health and gastrointestinal disease
Journal: Frontiers in Veterinary Science
- 目的: 犬の腸内細菌叢と代謝物が健康および疾患に与える影響を総説的に整理。
- 主な結果:
- 健康な犬ではSCFA産生菌のバランスが取れている。
- IBDや食事性下痢ではSCFA産生菌の喪失と炎症性菌の増加が認められる。
- ポイント: 臨床への応用(プロバイオティクス、プレバイオティクス)の可能性も論じている。
4. Mach N & Clark A. (2021)
Title: Insights from canine comparative microbiome studies: dysbiosis and therapeutic approaches in inflammatory bowel disease
Journal: Journal of Animal Science
- 目的: 犬のIBDにおけるマイクロバイオームの特徴と治療介入法をレビュー。
- 主な結果:
- 免疫・代謝・粘膜バリアに関与する菌群の減少が共通の特徴。
- 食事療法・プロバイオティクス・抗生剤の治療的影響に差がある。
- ポイント: 機能に着目した治療戦略の重要性を強調。
5. Lopez-Siles M, et al. (2017)
Title: Faecalibacterium prausnitzii: from microbiology to diagnostics and prognostics
Journal: ISME Journal
- 目的: Faecalibacterium prausnitzii の抗炎症作用とその臨床応用をレビュー。
- 主な結果:
- 酪酸産生・IL-10誘導などの抗炎症メカニズム。
- IBD患者では顕著な減少が見られ、バイオマーカーとしても有望。
- ポイント: 「機能的有益菌」として最も注目される種の1つ。
6. Zhang M, et al. (2022)
Title: Gut microbiota and mucosal immunity in canine inflammatory bowel disease
Journal: Veterinary Journal
- 目的: 犬のIBDにおける腸内フローラと腸管免疫の相互作用を総説。
- 主な結果:
- ディスバイオーシスがTregやTh17のバランスを崩す。
- 腸内細菌が抗炎症性サイトカイン(IL-10)やバリア強化に関与。
- ポイント: 犬の免疫と腸内細菌のクロストークに焦点を当てた貴重なレビュー。
7. AlShawaqfeh MK, et al. (2017)
Title: A dysbiosis index to assess microbial changes in fecal samples of dogs with chronic inflammatory enteropathy
Journal: FEMS Microbiology Ecology
- 目的: 犬の慢性腸症における腸内フローラの変化を「数値化」する指標(DI)を開発。
- 主な結果:
- 健常犬と慢性腸症犬で腸内フローラ構成が明確に異なる。
- Faecalibacteriumや Fusobacterium の減少、 Escherichia coli の増加が特徴。
- ポイント: 診断や治療モニタリングに有用な**Dysbiosis Index(DI)**を提案。
8. Everard A, et al. (2013)
Title: Cross-talk between Akkermansia muciniphila and intestinal epithelium controls diet-induced obesity
Journal: PNAS
- 目的: Akkermansia muciniphila の腸管バリアと代謝に対する影響をマウスで検証。
- 主な結果:
- 粘液分解によりバリア強化、インスリン感受性改善。
- 抗炎症性マーカー(例:IL-10)の増加。
- ポイント: 炎症性腸疾患に限らず、代謝疾患にも関与する有益菌としての可能性を示唆。
9. Oka A, et al. (2018)
Title: Probiotic Lactobacillus strains in the treatment of canine chronic enteropathies: A meta-analysis
Journal: Journal of Veterinary Internal Medicine
- 目的: 犬の慢性腸症に対するプロバイオティクス(特にLactobacillus)の有効性を評価。
- 主な結果:
- 投与群では炎症スコアや下痢の改善傾向が有意。
- 株ごとの効果にばらつきがあるため、“株選択”の重要性が強調される。
- ポイント: プロバイオティクス治療の科学的根拠を補強するデータ。

