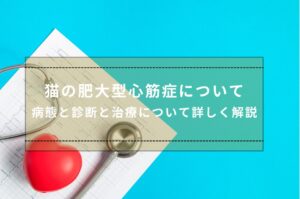犬の避妊・去勢は本当にするべき?
様々な研究から見るメリットとリスク
はじめに
「犬の避妊・去勢は必ずしたほうがいい」というのは、長年の常識でした。
しかし近年、獣医学の進歩とともに「本当に全ての犬に一律で勧めていいのか?」という疑問が浮上しています。
犬種や体格、生活環境に応じて、より個別化した判断が必要とされるようになってきたのです。
このブログでは、従来のメリットと、様々な研究で見えてきたリスクの両面から、避妊・去勢について冷静に解説します。
「うちの子には、いつ・どうするのがベスト?」と悩む飼い主さんの参考になれば嬉しいです。
犬の避妊・去勢、よく言われるメリットとは?
繁殖制御
避妊・去勢の最大の目的は望まれない繁殖の防止です。
無計画な妊娠を防ぐことは、動物福祉の観点からも非常に重要です。
行動学的メリット
去勢・避妊によって、
- 発情期のストレスを軽減
- マーキングやマウンティング、攻撃性、脱走などの問題行動が軽減
することがあります。
疾患予防
とくに注目されるのは、雌犬の避妊手術による乳腺腫瘍と子宮蓄膿症の予防です。
雌犬では、初回発情前に避妊手術を行うことで乳腺腫瘍のリスクが大幅に下がるとされ、
以下のような有名な統計があります:
- 初回発情前:発生率 0.5%
- 1回目の発情後:8%
- 2回目の発情後:26%
📌 このデータの出典について
これは1969年にSchneiderらによって報告された研究結果で、現在でも獣医師の教科書的な統計として広く知れ渡っています。
しかし、因果関係ではなく相関関係の分析に留まる事、当時の飼育状況や医療技術・診断制度の違い、犬種差や飼育環境の違いなど、研究デザインや診断精度の観点からは限界も多く、現代ではこの研究単独ではなく、後続の前向き研究や病理学的研究と併せて評価すべきとされています。最近の大規模調査では、乳腺腫瘍と避妊手術の関係はより複雑で、「発情回数」だけでは語れないこともわかってきています。
また、避妊手術は命に関わる子宮蓄膿症の予防にも非常に有効です。
その他、避妊手術により子宮の平滑筋肉腫の発生リスクが低下する事も考えられています。
雄犬においても、
- 精巣腫瘍
- 前立腺疾患
- 会陰ヘルニア
などのリスクを下げる効果があります。
これらの要素から、これまではどの犬種も画⼀的に 6 ヶ⽉前後での不妊・去勢⼿術が推奨されてきていた。
避妊・去勢による疾患発生リスク?
犬の避妊・去勢手術を行うメリットは上記のようなものが一般的に挙げられます。一方で、避妊・去勢を行うことで増加する疾患リスクについても最近の研究では報告されています。
有名なものとしては、体重増加とそれに伴う肥満関連疾患、大型犬に起こりやすい高齢期におけるホルモン関連性尿失禁などが挙げられます。
それ以外にも整形疾患(前⼗字靭帯断裂、肘関節形成不全症、股関節形成不全症、椎間板ヘルニア)、腫瘍性疾患(リンパ腫や⾎管⾁腫、肥満細胞腫、および⾻⾁腫)のリスクについても上がるのでは?という報告もあります。
骨関節疾患リスクの増加?
特に大型犬では早期の避妊・去勢手術で前十字靭帯断裂・股関節形成不全症といった骨関節疾患の発生率が高くなることが複数の研究で可能性が示されています。
これは成長板閉鎖には性ホルモンが関与している事が関係しているためではないかと考察されています。骨格が成長し終わる前に避妊・去勢手術を受けると、成長板閉鎖が遅延し、時期によっては関節形成に影響が生じ、将来的な関節疾患リスクが増すことが危惧されます。
特定の腫瘍リスクの上昇?
一部の疫学研究では、リンパ腫、肥満細胞腫、血管肉腫、骨肉腫などのがんリスクが、避妊・去勢手術を行うことによって上昇する可能性が報告されています。
- リンパ腫:様々な犬種を組み込んだ大規模調査において避妊・去勢手術でリスクが2倍ほど上がる
- 肥満細胞腫:犬種を無作為に組み入れた報告で、避妊・去勢手術によってメスでは3-4倍、オスでは1.2-1.3倍リスクが高くなる
- 血管肉腫:⾎管⾁腫と診断された⽝を対象に、避妊・去勢手術によってメスでは1.7-3.2倍、オスでは1.1-1.4倍ほどリスクが上がる
- 骨肉腫:犬種非特異的な研究で、避妊・去勢手術によって全体でリスクが2倍、メスでは2.5倍、オスでは1.6倍ほど上がる
などの疫学的研究報告があります。
避妊・去勢手術を行うことと腫瘍発生のリスクが上昇する事における直接的な因果関係はわかっておりませんが、避妊・去勢手術を受けた犬は未避妊・未去勢の犬よりも寿命が長くなる事と関連しているのではないかとも考えられています。避妊・去勢手術によって寿命が延長し、高齢期となったその結果として腫瘍の発生リスクが増えた可能性も示唆されています。
去勢・避妊に関する疫学的研究とバイアスの問題
去勢や避妊に関する研究や論文にはバイアス(偏り)がかかっている可能性があります。多くの避妊・去勢に関する研究は、特定の病院や診療所に来院する動物に基づいて行われています。これらの動物は、すでに健康上の問題がある場合や、獣医によって推奨された特定の年齢に手術を受けた場合が多いです。つまり、これらの研究が必ずしも「全ての犬」や「全ての猫」に当てはまるわけではないという点です。また、避妊・去勢に関する多くの研究は観察的研究であり、これは因果関係を明確にするのが難しいという問題があります。観察的研究では、他の要因(例えば、生活環境や遺伝的要素など)が影響を与える可能性があり、これを完全に制御するのは難しいことがあります。去勢や避妊に関する研究や論文は、ランダム化比較試験(RCT)のような実験的研究が行われることは少ないです。
【犬種・体格別】避妊・去勢のタイミングは変えるべきか?
一部の報告では犬種や体格ごとに手術の適齢時期を変えることが推奨されています。
| 犬のタイプ | 避妊・去勢の推奨時期 |
|---|---|
| 小型犬 | 生後6〜9か月前後 |
| 中型~大型犬 | 生後12か月以降が望ましい |
| 超大型犬(ロットワイラーなど) | 生後18か月以降を推奨するケースも |
※ 骨格の成長板閉鎖時期を考慮したもの
犬の避妊・去勢:メリット・デメリット早見表
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 望まれない繁殖の防止 | 骨関節疾患リスクの上昇(大型犬) |
| 乳腺腫瘍・子宮蓄膿症の予防 | 骨肉腫・リンパ腫など特定のがんリスク増加? |
| 精巣腫瘍、前立腺疾患、会陰ヘルニアの予防 | 基礎代謝低下による肥満リスク |
| 問題行動の軽減(脱走、発情ストレス) | 免疫・内分泌系バランスへの影響 |
まとめ ー 「うちの子」にとってベストな選択を
避妊・去勢手術は、多くの犬に恩恵をもたらす大切な医療行為です。
しかし、すべての犬に画一的に適用するには、いくつかリスクもあるかもしれないと指摘があります。そもそも、避妊・去勢に関する多くの研究は観察的研究であり、これは因果関係を明確にするのが難しいという問題があります。(わかってない事の方が多いと思われます。)
大切なのは、「避妊・去勢すべきか?」という二択ではなく、
「この子には、いつ・どうするのがベストか?」を一緒に考えることです。
また、我々獣医師は、動物業界の常識を疑いながらも、自分の考えを持ち、客観的な視点から飼い主さんの考えや愛犬の個性を大切にしながら、最善の選択ができるようサポートしていく必要があるのではないかと改めて考えさせられました。
LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで病気の予防関連でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。