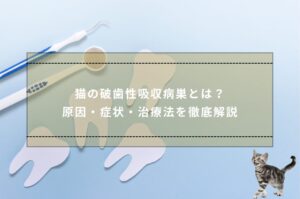【猫の歯肉炎の原因とは?】症状から対処法、動物病院を受診すべきサインまで解説
「最近、うちの猫の口が臭う…」「ごはんを食べづらそうにしている」
そんなときに考えられるのが歯肉炎です。
猫の歯肉炎は、比較的よく見られるお口のトラブルで、軽度であれば気づかれにくいこともありますが、放っておくと痛みや食欲低下、全身の健康にまで影響することがあります。
今回は、猫の歯肉炎の原因と症状、飼い主さんができる対処法や、動物病院を受診すべきタイミングについて詳しくご紹介します。
猫の歯肉炎とは?どんな状態?
歯肉炎とは、歯ぐき(歯肉)が赤く腫れたり、出血しやすくなったりする炎症のことです。猫では、若齢期から高齢期まで幅広い年齢で起こりえます。
- 歯ぐきが赤く腫れている
- 食べるときに痛がる・途中でやめる
- よだれが増える、口元がぬれている
- 口臭が強くなる
- 片側でしか噛まなくなる
こうしたサインが見られる場合、歯肉炎が進行している可能性があります。
猫の歯肉炎の原因とは?
1. 歯垢・歯石の蓄積(歯周病由来)
最も多い猫の歯肉炎の原因は、歯垢や歯石の蓄積です。食べかすが歯に残ると、細菌が繁殖し、歯と歯ぐきの間に炎症を引き起こします。
とくに2歳を過ぎた猫では、約7割が歯周病にかかっているとも言われており、日常的なデンタルケアをしていない場合、知らないうちに歯肉炎が進行してしまうことも。
2. 免疫異常・ウイルス感染
猫カリシウイルスや猫白血病ウイルス(FeLV)、猫エイズウイルス(FIV)などのウイルス感染によって、免疫機能が低下することで、慢性的な歯肉炎を引き起こすことがあります。こうした猫では、免疫介在性の口内炎(慢性歯肉口内炎)に進行するケースも多く、重度になると全顎抜歯が必要になることも。
3. 遺伝的な体質・若年性歯肉炎
若い猫(1〜2歳)で見られることが多い「若年性歯肉炎」は、特に純血種や長毛種で発症しやすいとされ、体質的に炎症を起こしやすい猫がいます。
この場合は、歯石がほとんどついていない状態でも強い歯肉炎を起こすことがあり、早期からの対応が重要です。
歯肉炎を放置するとどうなる?
歯肉炎が悪化すると、次のような状態に進行する可能性があります。
- 歯周炎(歯を支える組織まで炎症が波及)
- 歯のぐらつき、抜け落ち
- 強い痛みや食欲低下
- 顎の骨の破壊(重度の場合)
- 口腔内細菌が血流に乗り、腎臓・心臓病のリスク上昇
「たかが歯ぐきの腫れ」と油断せず、早期のケアが猫の健康寿命を守るカギになります。
自宅でできる対処法はある?
1. デンタルケアの導入
歯みがきが最も効果的ですが、嫌がる猫にはデンタルガム・口腔用ジェル・歯みがきシートなどから始めるとよいでしょう。毎日が難しくても、週に数回のケアが積み重なって効果を発揮します。
2. 歯垢がつきにくいフードを選ぶ
最近では、歯垢の蓄積を抑える成分を配合したフードやおやつも増えてきました。歯の健康維持に役立つアイテムを日常に取り入れてみましょう。
3. お口チェックの習慣を
定期的に口の中を観察することで、初期のサイン(赤み・口臭・痛がり)に早く気づけます。機嫌がいいときに軽くめくってチェックする習慣をつけましょう。
こんなときは動物病院へ
次のような症状が見られたら、歯肉炎が進行している可能性が高いため、早めの受診をおすすめします。
- 歯ぐきが明らかに赤く腫れている
- 食べたがるのに、途中でやめてしまう
- 片側の歯でしか噛まない
- よだれが増えた、血が混じる
- 口臭がきつくなった
- 顔まわりを触られるのを嫌がる
また、ウイルス感染歴のある猫や、若くして歯ぐきの炎症が目立つ猫も、定期的な歯科検診を受けることで、病気の進行を防ぐことができます。
まとめ|猫の歯肉炎は「放置しない」が鉄則!
猫の歯肉炎の原因は、歯垢・歯石だけでなく、ウイルス感染や体質、免疫異常など多岐にわたります。軽度なうちに気づいて対処することで、猫にとってつらい思いをさせずにすむだけでなく、全身の健康維持にもつながります。
気になる症状がある場合は、自己判断せず、ぜひ一度動物病院で口の中を診てもらいましょう。
大切な愛猫が健康に長生きできるよう、お口のケアも日々の習慣に取り入れてみてくださいね。
LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで病気の予防関連でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。
より詳しいコラム記事はこちら↓↓