犬の特発性角質肥厚とは?原因・診断・ケア方法を詳しく解説
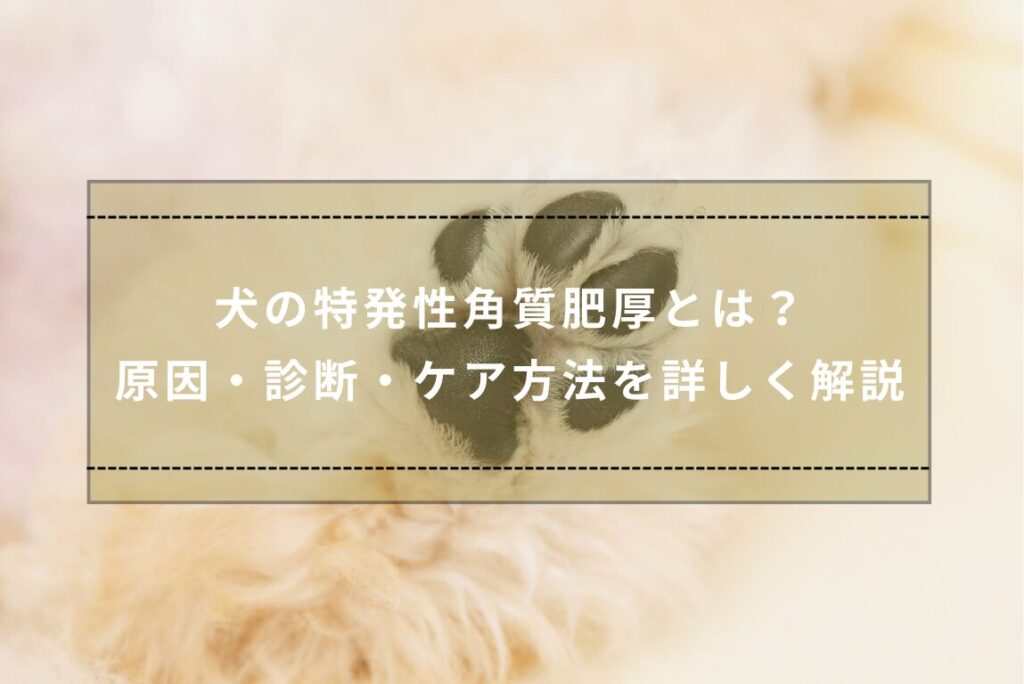
犬の鼻や肉球に「カサカサ」「ガサガサ」とした厚い角質が目立つことはありませんか?
とくに高齢犬でよく見られるこの状態は、「特発性角質肥厚(Idiopathic Nasodigital Hyperkeratosis)」と呼ばれる皮膚のトラブルのひとつですかもしれません。
見た目の違和感だけでなく、放置すると痛みやひび割れにつながることもあるため、早めのケアが大切です。
特発性角質肥厚の症状

写真のように、肉球の一部が灰褐色〜黒色の厚い角質で覆われ、表面が硬くゴワゴワしているのが特徴です。
初期は乾燥や軽いざらつき程度ですが、進行すると角質が盛り上がり、歩行時の違和感や出血を伴うこともあります。
主な見られる部位は次のとおりです。
- 鼻鏡(鼻の頭)
- 肉球(特に前足の中心部や指球)
- まれに肘などの圧迫部位
原因:なぜ角質が厚くなるの?
「特発性」と呼ばれるように、明確な原因が特定できないことが多いのがこの疾患の特徴です。
しかし、いくつかの要因が関与していると考えられています。
1. 遺伝的素因
コッカースパニエル、ラブラドールレトリーバー、ビーグルなど、一部の犬種で好発します。皮膚のターンオーバー異常が生じやすい遺伝的背景があると考えられています。
2. 加齢性変化
老齢犬では皮脂分泌や角化細胞の代謝が低下し、角質が硬く厚くなりやすくなります。
特に鼻や肉球は再生が遅く、乾燥や摩擦の影響を受けやすいため、好発部位となります。
3. 他の疾患に伴う場合
甲状腺機能低下症やジステンパー病の後遺症、自己免疫性疾患でも角質肥厚が見られることがあります。
したがって、見た目が似ていても、必ずしも「特発性」とは限りません。
診断方法
動物病院では、視診と触診を中心に以下のような流れで診断を行います。
- 臨床症状の確認
鼻や肉球に限局した乾燥・肥厚の有無をチェックします。 - 年齢・犬種・既往歴の確認
加齢性か、基礎疾患に伴うものかを判断する手がかりになります。 - 鑑別疾患の除外
血液検査でホルモン異常(甲状腺など)を調べたり、皮膚病変の細胞診を行うこともあります。
特に、若齢で急に角質肥厚が出た場合や、全身症状を伴う場合は他の疾患を疑う必要があります。
治療・ケア方法
特発性角質肥厚は完治するものではないため、定期的なケアで症状をコントロールする必要があります。
主な治療法と日常ケアのポイントを紹介します。
1. 角質の軟化・除去
- ワセリンや尿素クリーム、ラノリン配合の保湿剤を1日1〜2回塗布します。
- 痛みを伴う場合には、動物病院で軟化処置をした上で、過剰な部分をハサミで除去します。
- 無理に削ると出血や感染を起こすことがあるため、自己処置は避けましょう。
2. 保湿と保護
- 散歩前に保湿剤を塗布し、靴下型の保護カバーを使用するのも効果的です。
- 乾燥が進みやすい冬場は、加湿器を使うのもおすすめです。
3. 定期的な診察
角質肥厚の陰にホルモン異常や感染が隠れていることもあるため、初期は定期的な診察が安心です。
悪化時には感染予防のため抗菌外用剤や抗炎症薬を使用することもあります。
放置するとどうなる?
軽度の段階では見た目の問題だけに感じられますが、重症化するとひび割れから出血や細菌感染を起こすリスクがあります。
痛みのために歩行を嫌がるようになるケースもあり、結果的に運動不足やストレスにつながります。
飼い主さんにできる日常ケアまとめ
- 毎日のブラッシング時に肉球や鼻をチェック
- 保湿剤を使って乾燥予防
- 角質が硬くなったら病院で処置を相談
- 定期的に体調チェック(ホルモン検査なども含めて)
まとめ
特発性角質肥厚は命に関わる病気ではありませんが、放置すると慢性的な痛みや感染の原因になることもあります。
「硬くゴワゴワした肉球」が見られたら、動物病院で相談しましょう。
正しいスキンケアと定期的な診察で、愛犬の足裏と鼻を健康に保つことができます。
関連記事
LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!


茅ヶ崎市・藤沢市エリアで病気の予防関連でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。


