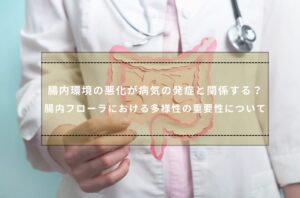犬の腸内フローラの多様性を高める方法|健康的な腸内環境を作る秘訣
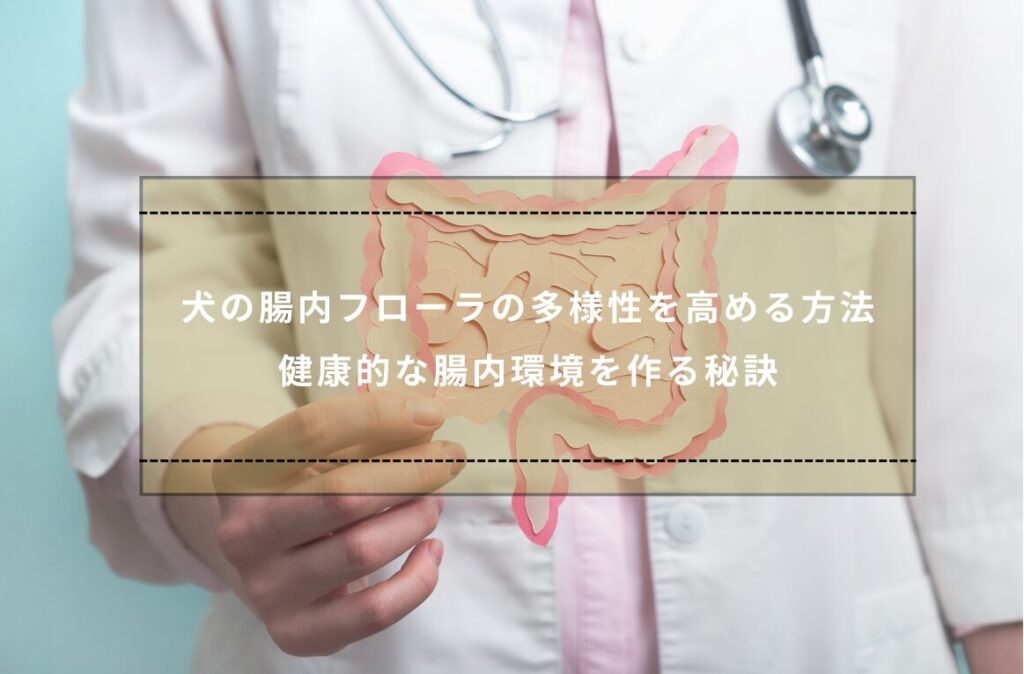
犬の腸内フローラの多様性を向上させることは、健康維持や免疫力向上に不可欠です。腸内フローラ(腸内細菌群)は、消化吸収をサポートするだけでなく、免疫機能や心身の健康にも大きな影響を与えます。腸内フローラの多様性が高いと、より健康的な腸内環境が維持され、愛犬の元気で長生きするための鍵となります。この記事では、腸内フローラを多様化させるための具体的な方法やおすすめの食事・サプリメントを詳しく解説します。
腸内フローラの多様性が犬にとって重要な理由
前回の記事では多様性の低下と病気の罹患率が相関する事を解説しました。とりわけ、消化器疾患と皮膚疾患においてはその傾向が強いと思われます。腸内フローラの多様性が高いということは、善玉菌と悪玉菌がバランスよく共存していることを意味します。これにより、免疫システムが適切に働き、有害な病原菌に対する抵抗力が強化されます。また、消化管の健康も維持され、便通がスムーズになり、愛犬の体調が整いやすくなります。
腸内フローラを多様化させるキーワードは「プレバイオティクス」
では腸内フローラの多様性を高めるにはどうしたら良いでしょうか?その答えは「プレバイオティクス」です。プレバイオティクスとは善玉菌の餌となり、腸内環境において有益となる食物繊維の事を言います。平たく言えばオリゴ糖です。オリゴ糖にはガラクトオリゴ糖(GOS)やフラクトオリゴ糖(FOS)マンナオリゴ糖(MOS)アラビノキシランオリゴ糖(AXOS)などがありますが、最近ではフラクトオリゴ糖の1種である「ケストース」が腸内細菌コントロールに役立つ「高機能プレバイオティクス」の代表格として注目されています。
関連記事:犬の健康は腸内環境から!腸活に必要なプレバイオティクスについて
高機能プレバイオティクスのケストースとは?
ケストースは、主にビフィズス菌などの特定の善玉菌の増殖を助けるプレバイオティクスとして働きます。ビフィズス菌はケストースを非常に効率的に利用できるため、ケストースを摂取することでビフィズス菌が急速に増加することが期待されます。
ビフィズス菌が急速に増加することで腸内環境が弱酸性に傾き、酸に敏感な病原性細菌が住みづらい環境づくりに貢献します。その後、ビフィズス菌によって生成される短鎖脂肪酸などが他の善玉菌(乳酸菌や酪酸菌)の増殖を促進するため、最終的には善玉菌優位な多様性が増加した腸内環境となります。
ケストース投与を開始した際、腸内フローラが急激に変化することにより、腸内の微生物群が不安定になり、腸内環境が一時的に乱れます。このような変化は、腸内での発酵やガスの生成、便の異常などを引き起こす可能性があり、これが一過性の下痢といった消化器症状につながることもあります。
ケストース VS 他のオリゴ糖
オリゴ糖にはさまざまな種類があります。代表的なものにフラクトオリゴ糖(FOS)やガラクトオリゴ糖(GOS)があります。これらも消化されにくく腸内で善玉菌(ビフィズス菌やラクトバチルスなど)の成長を助けます。オリゴ糖はその種類によって、影響を受ける腸内細菌の種類が微妙に異なります。よって「1種類のオリゴ糖」と、「複数種のオリゴ糖の併用」では、後者の方が腸内多様性の向上に貢献する他、特定の細菌グループの突出を回避できるなど、大きなメリットがあります。
ケストースは、単剤でも長期的な面では全体的に有益菌有利な多様性の増加に貢献しますが、投与開始した際に腸内フローラが急激に変化する事で、一時的に腸内環境が乱れます。腸活を開始するきっかけが下痢で悩んでいるケースも多いため、これは大きなデメリットになります。
個人的な意見としては、ケストースを含めた複数のオリゴ糖を組み合わせる事で、急激な腸内環境の変化を起こす事なく全体的に多様性を上げる事が好ましいのでは?と考えます。
多様化を促す食事管理は?
犬の多様化も促し腸内環境を整えるために食事を選ぶ際には、いくつかのポイントを考慮することが必要です。腸内環境が整うと、消化不良や下痢、便秘などの問題が軽減され、免疫力の向上や全体的な健康維持にも役立ちます。
消化吸収の良い原材料を使用しているか?
「消化の良さ」は腸内環境を整える上で最も重要な要素です。特に注目すべきはタンパク質です。未消化なタンパク質だと、それが悪玉菌の餌となり、腸内環境の悪化に繋がります。加水分解食(消化管の中でタンパク質がアミノ酸レベルまで分解されるよう処理された食事)や低アレルゲンな食材(例えばラム肉、白身魚、ポテトなど)は、アレルギーや食物不耐性がある子には特にお勧めです。
脂肪の質と量
腸内環境を良好に保つためには、健康的な脂肪(オメガ-3脂肪酸やオメガ-6脂肪酸)が重要です。特にオメガ3脂肪酸は、腸内の炎症を軽減する効果があるとされています。また、過剰な脂肪分は腸粘膜のリンパ管に負担をかけるため、適切な量の脂肪が含まれているかチェックしましょう。一般的に脂肪が20%以上である食事は高脂肪食とされます。特に制限がなければ10〜15%範囲のものがお勧めです。
食物繊維の量と種類
食物繊維は、腸内フローラの健康を保つために非常に重要です。食物繊維は腸内の善玉菌の餌となり、便通を正常化し、腸内の有害物質を排出する助けにもなります。製品によっては繊維質に加え、フラクトオリゴ糖(FOS)やマンナンオリゴ糖(MOS)を別で添加しているものもあります。当然これらの成分は、腸内の善玉菌を増やし、有害な菌の抑制に効果があります。
腸内環境をサポートするビタミンとミネラル
ビタミンA、ビタミンE、ビタミンCなどの抗酸化物質や、腸内の修復を助ける亜鉛などのミネラルは腸内環境の改善に役に立ちます。またビタミンB12は腸粘膜の再生を促す上で重要です。これらの栄養素がバランスよく含まれている食事も選ぶポイントになります。
手作りのトッピング
完全な手作り食を実施する場合、栄養基準を満たす栄養素は25項目もあり、毎日これら全てを網羅するのは中々の労力がかかります。そのため、ベースは上記項目を満たすような総合栄養食とし、そこに手作りのトッピングを加えるといった工夫を行うのも良いかと思います。
例えば、かぼちゃ・ブロッコリー・バナナにはイヌリン(フラクトオリゴ糖)が含まれており、さつまいもにはペクチンと呼ばれる可溶性繊維やレジスタントスターチと呼ばれる不溶性繊維が含まれております。これら野菜を細かく刻んで、茹でる・蒸すなどの処理を施してからトッピングすると良いでしょう。トッピングの目安量は総合栄養食全体の10〜20%以下に抑える事が理想的です。
まとめ
犬の腸内フローラを多様化させることは、健康維持にとって非常に重要です。バランスの取れた食事やサプリメントの活用を通じて、愛犬の腸内環境を整えることができます。腸内フローラの多様性を高めることで、愛犬の免疫力が向上し、元気で健康な生活を送ることができるでしょう。
愛犬の腸内環境を守るために、ぜひこれらの方法を実践して、健やかな毎日をサポートしてあげてください。
関連記事
LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで消化器症状や皮膚の痒みでお悩みの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。