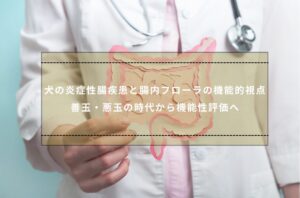猫の心筋症と動脈血栓塞栓症(ATE)|突然の後ろ足マヒに要注意!
猫が突然後ろ足を引きずったり、歩けなくなったりしたら要注意。それは**動脈血栓塞栓症(ATE)**かもしれません。この病気は、心筋症という心臓の病気と深く関係しており、早期発見と予防が命を守るカギになります。
この記事では、猫の心筋症とATEの関係、症状、検査、治療、予防法までわかりやすく解説します。
より詳しいコラムはこちら↓↓
猫の心筋症とは?〜心臓の病気が引き起こす大きなリスク
心筋症とは
心筋症とは、心臓の筋肉(心筋)が異常をきたす疾患で、猫では特に「肥大型心筋症(HCM)」が多く見られます。
猫に多い心筋症の種類
- 肥大型心筋症(HCM):心筋が厚くなり、心臓の動きが悪くなる
- 拡張型心筋症(DCM):心筋が薄くなり、収縮力が低下(まれ)
- 拘束型心筋症(RCM):心筋が硬くなり、拡張しにくくなる(高齢猫に多い)
心筋症の怖い合併症
心筋症が進行すると、心臓内に血の塊(血栓)ができやすくなり、それが動脈に詰まることで「動脈血栓塞栓症(ATE)」を引き起こします。
動脈血栓塞栓症(ATE)とは?
突然やってくる「血栓症」
ATEは、心臓でできた血栓が体の動脈に詰まってしまう病気です。特に後ろ足を支配する「大腿動脈」に詰まるケースが多く、激しい痛みや麻痺を引き起こします。
ATEの主な症状
- 突然の後肢マヒ・歩けなくなる
- 強い痛みで鳴き叫ぶ・嘔吐する。
- 後ろ足が冷たくなる(血流が止まっているため)
- 肉球が青紫になる
- 呼吸が速くなる(心疾患による影響)
ATEは突然発症し、命に関わる緊急疾患です。
どうやって診断するの?
心臓病の確認には「心エコー検査」が重要
- 心筋の厚みや動き、心房の拡大などをチェック
- 血栓が見えることもある
- ATEの予防や早期発見にも有効
血液検査・X線検査・心電図なども併用
- 呼吸困難がある場合は胸水や肺水腫の確認も必要
- NT-proBNP(心臓負担マーカー)の測定も有用
治療法:ATEの緊急処置と心筋症の長期管理
ATE(動脈血栓塞栓症)の治療
- 鎮痛剤(強い痛みへの対応)
- 抗血栓療法(ヘパリン、クロピドグレルなど)
- 酸素吸入・循環サポート
- ※外科的血栓除去は猫ではリスクが高いため、通常行われません
心筋症の治療
- 利尿薬・β遮断薬・カルシウム拮抗薬などで心負担を軽減
- 抗血栓薬の継続使用(予防目的)
- 定期的な心エコー検査で経過観察
飼い主さんにできること|予防と早期発見のポイント
家でのチェックポイント
- 息が荒い、胸や腹が大きく動いている
- 歩き方が変、ジャンプを嫌がる
- 肉球や耳が青白い・冷たい
- ぐったりしている、食欲がない
これらは心疾患や血栓症のサインかもしれません。
定期検診の重要性
- 特にメインクーン・ラグドール・スコティッシュフォールドなどは心筋症の好発品種です
- 高齢猫や、過去に血栓症を経験した猫も要注意
- 心エコー・血液検査を定期的に受けましょう
まとめ
猫の心筋症は見た目にわかりにくいことが多く、症状が出たときにはすでに重症化していることもあります。動脈血栓塞栓症は突然起こるため、予防と早期発見がとても大切です。
少しでも異変を感じたら、すぐに動物病院での診察を受けましょう。
LINE友だち追加で診察予約・最新情報がチェックできます!!

茅ヶ崎市・藤沢市エリアで犬猫の心臓病でお悩みの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。