犬猫の消化器疾患における食物繊維の重要性と使い分けについて
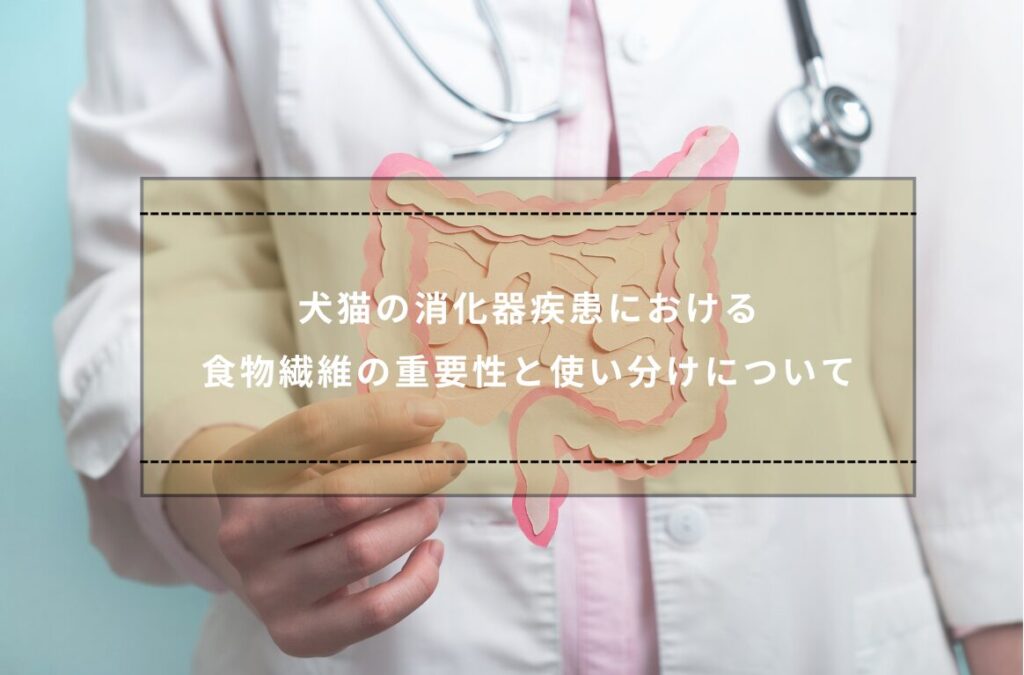
食物繊維は、消化管の恒常性を維持するうえで欠かせない“非消化性炭水化物”です。下痢や便秘の改善、腸内細菌叢のバランス維持、腸粘膜の保護など、多くの生理作用に関与しています。ただし、食物繊維は種類や添加量によって効果が大きく異なるため、症状や目的に応じた使い分けが重要です。
本記事では、犬猫の下痢(急性・慢性)、便秘、毛玉症などの消化器トラブルに対し、どのように食物繊維を選択・活用すべきかをわかりやすく解説します。
食物繊維とは?
炭水化物のうち、体内で消化・吸収され、エネルギー源となるものを「糖質」、体内で消化・吸収されずほとんどエネルギー源にならないものを「食物繊維」と言います。
食物繊維の主な役割としては以下のようなものが挙げられます。
- 消化管内容物の物理的変化:繊維が便の体積を増やしたり、通過速度に影響を与える
- 微生物発酵の基質:一部の食物繊維は腸内細菌によって発酵され、短鎖脂肪酸(SCFA)などを供給。これが腸内環境や全身への代謝・免疫への影響を持つ。
- 消化調整:水分保持能力や腸運動への影響を通じて消化過程を調節
- 食欲・満腹感の調節:粘性のある食物繊維では胃腸の滞留を促し、満腹感をサポート
これらの機能により、消化管の恒常性維持や腸内細菌を介する免疫の調整といった重要な役割を担います。
食物繊維の分類
食物繊維は、その構造から一般的に「可溶性繊維」と「不溶性繊維」に分類されます。しかし実際には、両方の性質を併せ持つものや、可溶性であっても“発酵性の有無”によって作用が変わるものもあります。このため、臨床や栄養管理の現場では、構造よりも機能性に基づく分類の方が実用的と考えられています。
機能性による主な分類は以下の3点です。
- 可溶性・不溶性(溶解性)
- 可溶性繊維: 水に溶けてゲル化し、粘稠性を示す。
- 不溶性繊維: 水には溶けないが水分を吸収し、便量を増やす。
- 粘稠性(粘度)
ゲル化の程度を示し、粘稠性が高いほど胃腸の通過速度を遅らせ、血糖抑制や満腹感の維持に寄与する。 - 発酵性
腸内細菌による発酵の速度や程度を示す。
非発酵性 → 徐発酵性 → 速発酵性の順で、腸内でのガス産生や短鎖脂肪酸の生成量が異なる。
このように、食物繊維は“何性か”よりも“どのように作用するか”で選ぶことが実践上重要です。
可溶性・高発酵性食物繊維
例:イヌリン、フラクトオリゴ糖(FOS)、ペクチン、βグルカンなど
特徴
・いわゆるプレバイオティクス
・腸内細菌により素早く発酵→SCFA(酢酸・プロピオン酸・酪酸)を産生
・これにより腸粘膜の機能改善、免疫調整、腸内細菌叢の改善
・多すぎると、逆にガス増加・下痢軟便を誘発
用途
・慢性腸症
・慢性特発性大腸性下痢
・抗生物質後の腸内環境回復
より詳しい記事はこちら↓↓
可溶性・中〜高粘稠性
例:サイリウム
特徴
・水分保持能力が高く、ゲル状になり便の形成を助ける
・下痢にも便秘にも使える「両方向性」の繊維で即効性がある
・大腸の蠕動を正常化
・サイリウムは発酵性がないのでプレバイオティクスとしての機能はない
・発酵性ではないのでガスが出ない
用途
・急性下痢
・慢性特発性大腸性下痢
・便秘(特に猫)
・毛玉症
不溶性・低発酵性食物繊維
例:セルロース
特徴
・水分を含んで便をかさ増しする事で、腸管の通過速度を促進
・ほとんど発酵されないため、ガスが出にくい
・水分を十分に摂取していないと、水を含まない便のかさ増しとなるため、便秘を悪化させるリスクがある
用途
・便秘
・毛玉症
・肥満管理
混合繊維
例:ビートパルプ
特徴
・可溶性と不溶性の両方の性質を持つ
・ビートパルプは80%が不溶性、20%が可溶性
・便の質をバランスよく整える万能型(下痢にも便秘にも有効)
・粗繊維としては高い消化率(40〜60%程度)
・メリットの多さ・デメリットの少なさから、多くの消化器系療法食に使われている
用途
・急性下痢後の回復期
・慢性特発性大腸性下痢
・慢性腸症
・便秘
病態別:推奨される繊維の組み合わせ
①急性下痢
推奨タイプ
◎可溶性粘性繊維(サイリウム)
◎混合繊維(ビートパルプ)
◯可溶性発酵性繊維(FOS、イヌリンなど)
◯不溶性繊維(セルロース)
ポイント
・水分調整とバリア機能回復
・サイリウムは水分吸着で便性改善に最も即効性がある
・24–48時間で便質改善を確認、必要なら微調整
・過剰な可溶性発酵性繊維はガス増加や下痢の悪化の懸念があるので、少量から開始する
②慢性特発性大腸性下痢
推奨タイプ
◎可溶性粘性繊維(サイリウム)
◎可溶性発酵性繊維(FOS、イヌリンなど)
◎混合繊維(ビートパルプ)
△不溶性繊維
ポイント
・いわゆる『繊維反応性腸症』に該当する。過敏性腸症候群(ストレスが関連する下痢)も反応が見られる
・サイリウムやビートパルプで便の形状を安定化させ、FOS/イヌリンでSCFA産生し、粘膜の再生を促す
・1〜2週間で臨床症状の改善
・ガスが多い場合には可溶性発酵性繊維を減量し、不溶繊維を微量追加
③慢性腸症
推奨タイプ
◎可溶性発酵性繊維(FOS、イヌリンなど)
◯混合繊維(ビートパルプ)
◯可溶性粘性繊維(サイリウム)
ポイント
・腸粘膜機能低下・バリア機能崩壊・ディスバイオシスが主体のため、可溶性発酵性繊維で腸内環境改善化を促す
・過剰な可溶性発酵性繊維はガス増加や下痢の悪化の懸念があるので、少量から開始する
・腸内細菌叢の変化・定着には1ヶ月〜数ヶ月要する
・サイリウムやビートパルプは便の形状の安定化に貢献
より詳しい記事はこちら↓↓
④便秘症
推奨タイプ
◎可溶性粘性繊維(サイリウム)±不溶性繊維(セルロース)
◯混合繊維(ビートパルプ)
ポイント
・不溶性繊維は水分を吸収して便をかさ増しする事で、腸管の通過速度を促進する
・水分が少ない状態だと、水を含まないで便のかさ増しとなるため、逆に便秘を悪化させるリスクがある
・サイリウムと組み合わせる事で、これを解消するので、安全策ではサイリウムから始めて不溶性繊維を追加するほうが無難である
⑤毛玉症(猫)
推奨タイプ
◎不溶性繊維(セルロース)
◯可溶性粘性繊維(サイリウム)
ポイント
・胃腸通過を改善し、毛の塊を小さく分散する
・気質的便秘の悪化を防ぐ
⑥抗菌薬後のdysbiosis(腸内環境悪化)
推奨タイプ
◎可溶性発酵性繊維(FOS、イヌリンなど):低容量
◯混合繊維(ビートパルプ)
ポイント
・腸内細菌叢の回復を促し、SCFA産生を改善
・ガスを抑えるため少量から開始が重要
食物繊維を使う際の注意点
1. 多すぎる繊維は下痢を悪化させる
→ 特に発酵性繊維はガス・腹鳴の原因になりうる
2. フードの繊維量を必ず確認
→ 追加繊維を入れる前に、元のフードの成分(NDF/ADF/粗繊維)を評価
3. 水分摂取を忘れない
→ 特に猫の便秘では最重要
4. 効果判定期間は症状によりけり
→ 早期中止は効果判定を誤る
急性下痢:1週間以内
慢性大腸性下痢:1〜2週間
慢性腸症の腸内細菌叢の定着:1ヶ月〜数ヶ月
まとめ
食物繊維は、消化器疾患の栄養管理において非常に重要な“治療的ツール”です。薬剤だけに頼るのではなく、食事介入として適切に組み込むことで治療効果を大きく高めることができます。そのため獣医師は、フードラベルに記載されている繊維量や繊維の種類を正しく読み解き、各症例の病態に応じた最適な“繊維戦略”を設計することが求められます。
関連記事
LINE友だち追加で診察予約、病院の最新情報はinstagramからチェックできます!!


辻堂・茅ヶ崎市エリアで犬猫の消化器症状でお困りの方は湘南ルアナ動物病院(湘南Ruana動物病院)までお気軽にご相談ください。


